毎日発信 今朝のLINKED通信
今の疾病に関する気になる情報を毎日発信しています。
今の季節だから流行る病気や対策など、いち早く知って予防しましょう。

緊急事態宣言や特措法の改正で何が変わる?
首都圏を中心に、新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかかりません。
医療の逼迫を何とかするために、東京都と埼玉県、千葉県、神奈川県は1月2日、政府に対して緊急事態宣言を発出するよう求めました。
政府はこの要請を受け止めて検討すると同時に、特措法改正案の取りまとめを急ぐ方針です。
さて、緊急事態宣言や特措法の改正で、どんな対策が立てられるのでしょうか。
緊急事態宣言が再び出されると…。
緊急事態宣言は、2020年3月13日に成立した特措法(新型インフルエンザ等特別措置法)に基づく措置です。
緊急事態宣言が出されると、対象地域の都道府県知事は住民に対し、感染防止に必要な協力を強く要請できるようになります。
具体的には、不要不急の外出の自粛、飲食店の休業要請、学校や福祉施設などの使用制限の指示、臨時の医療施設の開設などについて権限を持つことになります。
特措法が改正されると…。
では、特措法が改正するとどうなるでしょうか。
現在、感染地域の知事たちは、飲食店などに営業時間の短縮を要請していますが、協力の要請にとどまっています。
特措法を改正することで、それをより強くすることができます。休業や時短の要請に応じた事業者への財政支援、反対に、要請に応じない事業者への罰則が盛り込まれる方向だということです。
緊急事態宣言、あるいは特措法改正。戦略の行方はまだわかりませんが、こうした方策が、感染拡大の速やかな抑制につながることを祈るばかりです。
NEWS
リンクト通信
アーカイブ
今週の
サポーター情報
REPORT
Special Thanks
画像提供:PIXTA
中日新聞リンクト編集部からのお願い
皆さまからいただくコメント・ご意見が、私たちの活力になります。より良いサイトづくりのため、皆さまの投稿をお待ちしておりますので、ぜひ下記投稿欄からお気軽にコメントください!
(各病院への診療に関する質問・相談等はこちらではお答えできませんのでご了承ください)






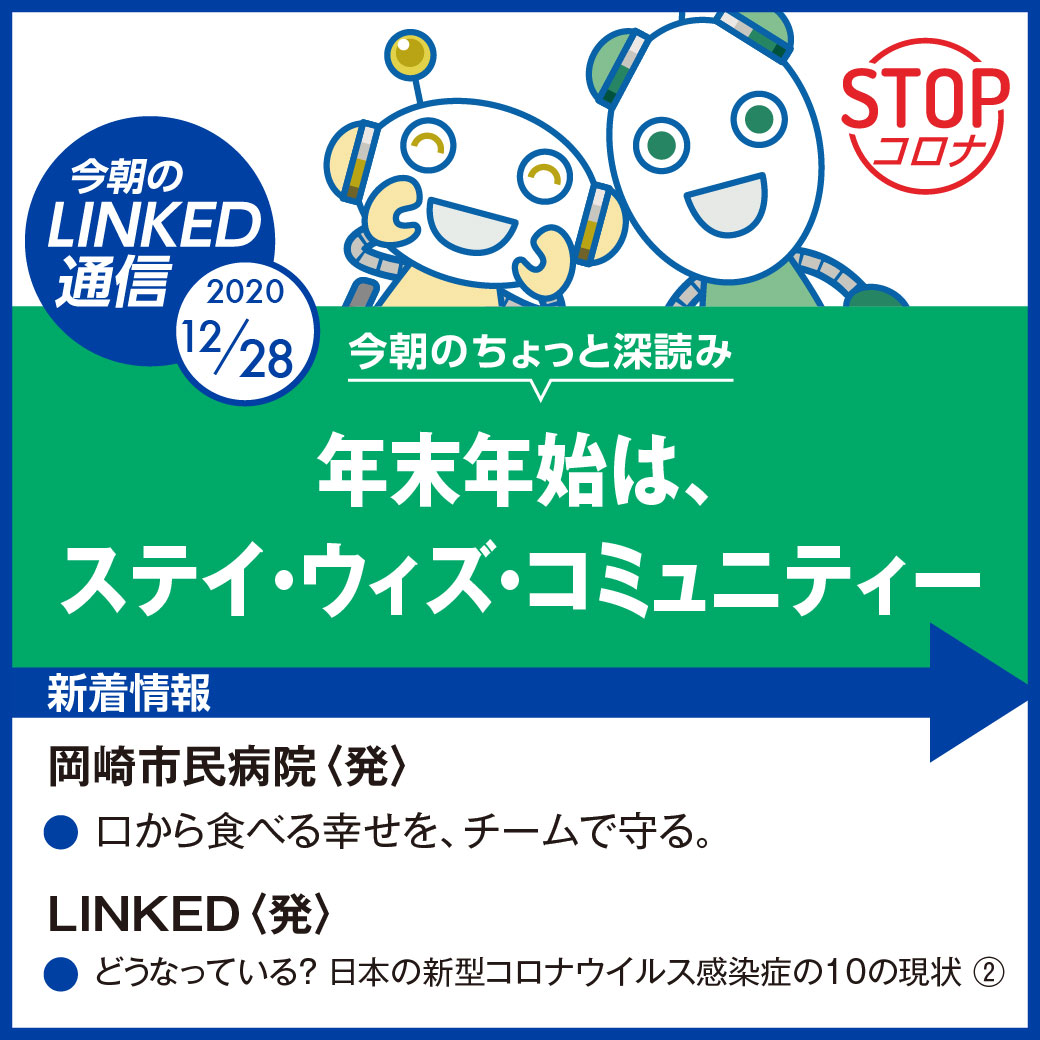

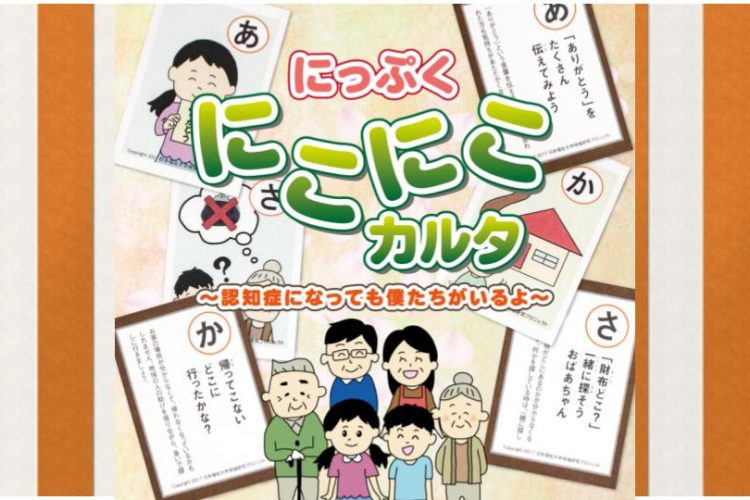





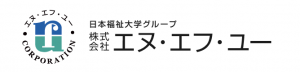
コメントを残す